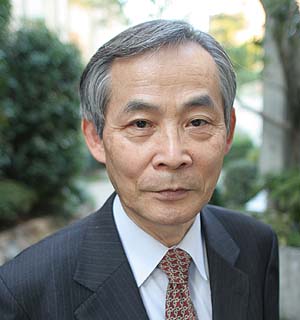歴史教科書に著作権なしか
疑問ある東京地裁判決
他社記述流用が増える恐れ
昨年、年の瀬も迫った12月19日、東京地裁(東海林保裁判長)で、歴史教科書には著作権はないというまことに奇妙な判決が出た。
訴訟の原因となる事件はこうである。扶桑社という出版社の子会社である育鵬社という出版社が発行し、平成24年より使用している中学校歴史教科書「新しい日本の歴史」が、同じく扶桑社から発行し平成18年から平成22年にかけて使用していた中学校歴史教科書「改訂版 新しい歴史教科書」から、その教科書の著者の許諾を得ず無断でその記述を流用していたというもので、端的にいって教科書の著作権侵害である。
扶桑社がそれまで出版し協力していた「新しい歴史教科書をつくる会」(以下「つくる会」)のメンバーが著述する教科書の出版を中止し、別に独自に教科書を制作し出版するとしたことから起こった問題であるが、その際に、それまで出版し続けていた「つくる会」側の著者の記述を無断で流用していたのである。
どの程度無断で流用し酷似しているかについては、「つくる会」が平成24年に発行した「歴史教科書盗作事件の真実」(自由社)に詳しいのでそれを見ていただきたいが、47カ所にわたってほとんど同一の記述が出てくる。
だから、その原著者が著作権を侵害されたとし訴えた。
これに対して、東京地裁は、両教科書に酷似する共通部分のあることを認めながら、「それら共通部分はいずれも歴史的事実や歴史認識それ自体であって表現ということができないものであるか、あるいは、事項の選択・配列及びその具体的表現内容のいずれにおいても創作性を認めることはできないものである」(判決文)として、このような酷似する教科書でも著作権の侵害はしていないとしたのである。例えば、「1192年、源頼朝が鎌倉幕府を開く」という記述は単なる歴史的事実の記述であり、ありふれた歴史認識の記述に過ぎず、この記述自体には著作権は存在しないのは当たり前だ。東京地裁は、この事実をもって、歴史教科書のすべてのこまごまとした記述には著作権は成立しないから、それゆえにその総和としての歴史教科書には著作権は存在しないとしたのである。
この論はもともと裁判が始まるまでは流用の事実を事実上認めていたにもかかわらず、裁判が始まって急に言い出した被告の主張する論なのである。原告は裁判の過程で、このような被告の論を採用すれば、他社の教科書をそのまま複製して発行してよいことになるではないかと、明確に反論していた。
実は、原告が関係するやはり歴史教科書に関する裁判で、歴史教科書における個々の記述にはこのような著作権が成立しない問題があるゆえに、教科書としての著作権は、①表現の視点、②表現すべき事項の選択、③表現の順序(論理構成)、④具体的な表現内容の4点において認証することができるという判決(東京地裁平成20年〈ワ〉第16289号書籍出版等差止請求事件判決)を下していた。原告はこの判決をも当然提示した。
今回の東京地裁の判決は歴史教科書の著作権にかかわる4点の基準をことごとく否定し、一般書で言える著作権の侵害をしない場合をそのまま歴史教科書に当てて、著作権の侵害はないとしたのである。
ここまで来ると、裁判官はこの判決が間違った判決であるという認識を持ちながら、原告を負けさせるためにあえて下した判決だと言うよりほかはないのではないか。
明らかに特定意図を持った偏向判決だ。判事たちは原告や「つくる会」に敵意を持っていたに違いない。裁判官も人間だから、特定の原告や被告に敵意を抱くかもしれない。しかし敵意を抱いても、争いごとに対してはその争いごとの限りにおいて、公正に判決を下すのが職業としての裁判官の務めではないか。判決を下す際、負ける側が判決に対していっさい反論できないという裁判制度を濫用して、ならば他社の歴史教科書をそっくり真似て制作し発行しても著作権の侵害にならないのかという原告の反論を無視して下した判決である。司法の権威を明らかに落としている。
本論は直接に原告や原告の属する「つくる会」のために論じているのではなく、社会の公正さ、法秩序の維持のために論じているものであるが、それにしても「つくる会」は大きな課題を負ったものだ。歴史教科書に嘘まで書いて日本を貶(おとし)める必要はないであろうと、日夜、健全な国家、社会の建設のために頑張っている「つくる会」の姿を、多くの人々は誤解しないで素直に見てほしい。
冒頭で述べたように、このような偏向の判決を得て、勝った扶桑社や育鵬社は沈黙し、負けた「つくる会」の側がこの判決の喧伝(けんでん)に努めているのは奇妙であり、この判決がいかに公正さを欠いたものであり、不健全なものであるかを明らかにしている。
(すぎはら・せいしろう)