[会員向け] 
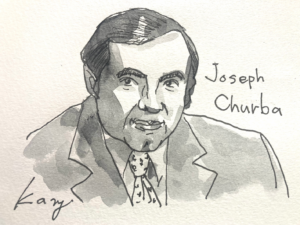
国際安全保障協議会「セントルイス宣言」の慧眼①
1983年のワシントン・タイムズ社長室での出来事である。 ある日、珍しいお客様が訪ねて来た。彼はユダヤ人学者として国際問題、特に国家安全保障問題の最高権威者であった。彼の名前はジョセフ・チャーバ博士(Dr.Josep…

ゴルバチョフの前に「人参」を吊せ
この時、文鮮明先生が登場されたのである。先生の主張は、「どちら側も信じる必要はない。ゴルバチョフの前に人参を吊せ。そして、改革の真実度を計る物差しを明白に設定せよ」というものであった。これはすなわち、”大統…

揺れるブッシュ政権—ゴルバチョフ改革は本物か?
私は先に、文鮮明先生が共産主義の脅威と闘い、宗主国ソ連を解放するためにアメリカに行き、レーガン大統領の誕生に全精力を注ぎ、その後にはワシントン・タイムズを創刊して、ソ連の世界赤化の野望を粉砕するうえで決定的な仕事をされ…

文鮮明師のソ連解放戦略
文鮮明先生がある時、ソ連が崩壊する道には三種類あると語られたことがあった。 第一に、軍事革命が勃発して連邦政府を転覆する道である。 第二に、窮地に追いやられ、のっぴきならない事態に陥ったソ連が、最後の手段として第三…

ゴルバチョフ改革—ペレストロイカとグラスノスチ
ゴルバチョフ書記長は危機的な国内経済を立て直し、ソ連社会を活性化するために、重荷になっている軍事費を削減して、東西体制の共存、より正確に言えば米ソ共存の道に踏み出そうとした。西側の支援なしにはソ連が窮地を抜け出す道はな…

ゴルバチョフ登場
アメリカ政府が対ソ戦略で大々的な攻勢に打って出たこの時期に、ソ連は国内経済だけでなく、政治体制にも緩みが見え始めた。原因は相次ぐ最高権力者の死である。まず1982年には、世界赤化戦略の権化(ごんげ)であるブレジネフ書記…

経済が疲弊しSDIで追いつめられたソ連②
ここで予期せぬ事態が発生した。「いや、こんなはずではないんだが?」と呆気に取られている間に、アメリカでレーガン大統領が当選したのである。これはソ連のシナリオにない出来事であった。ソ連の目論見は容共的なカーター大統領の再…

経済が疲弊しSDIで追いつめられたソ連①
ソ連の赤い版図が大きくなればなるほど、ソ連の経済力は打撃を受け始めた。一つの国を拾って手に入れるたびに、その分だけ宗主国であるソ連の負担は大きくなる。ソ連は同盟国キューバのために、一日平均100万ドルもの支援をしなけれ…

ソ連帝国の版図を押し広げたブレジネフ時代②
1968年、ドプチェク共産党第一書記が「人間の顔をした社会主義」のスローガンを掲げて、言論・思想の自由、複数政党制などの改革を推し進め、広範な大衆の支持を得た。これに危機感を抱いたソ連はワルシャワ条約機構軍を動員して介…
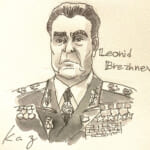
ソ連帝国の版図を押し広げたブレジネフ時代①
<前の記事 それでは、1976年のワシントン・モニュメント広場大会から1990年の「文—ゴルビー会談」までの約14年間に、ソ連はどのような変遷を辿ってきたのだろうか? 私は既に、文鮮明師の「ソ連内部で地殻変動にも等し…

頭翼思想に関心示したソ連の指導者たち
実を言うと、ソ連の指導者たちは文鮮明師の頭翼思想に大きな関心を抱いていた。 彼らは最初のうち、文鮮明師が単なる極右分子で、なんとしてもソ連を屈服させようという陰謀から、あるいは西欧式民主主義を無理にでも移植しようとい…

世界的な大混乱を収拾する「第3の道」②
民主主義と共産主義の欠陥を見ると、この新文化革命は神を中心とする絶対的価値の基盤の上にのみ可能であると結論づけることができます。それは決して変化する現象に立脚した相対的価値からは創出することができません。その思想は宇宙…

世界的な大混乱を収拾する「第3の道」①
文先生はアメリカでは、1976年のマンモス大会(ヤンキー・スタジアム大会、ワシントン・モニュメント広場大会など)で神主義を大胆に宣布され、それ以後も世界各地で、機会あるごとにこの理念を訴えてこられた。 1983年11…

人類歴史は神を探し求めていく茨の道②
神は人間をご自分とそっくりに創造された。したがって、人間は神の似姿であり、両者は相似形である。もう少し分かりやすく表現すれば、神は目に見えない人間であり、人間は目に見える神である、と言って差し支えない。ところが、「目に…

人類歴史は神を探し求めていく茨の道①
この勝共思想は「神主義(Godism)」、またはその別名である「頭(とう)翼(よく)思想」に根拠を置く。左翼でもなく右翼でもないこの頭翼思想は、ソ連の共産主義指導者たちを懐柔し、コルバチョフ大統領との会談を実現するのに…
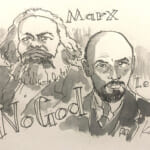
「共産主義解放」は“滅共”ではない
「ソ連が変われば世界が変わる」——これは最初から文鮮明先生の信念であった。そして、文先生は“ソ連帝国の終焉” “国際共産主義の解放”こそメシヤ・救世主たるご自身の最大の使命であると鉄石のごとく信じておられた。「神はいな…

世界言論人会議など3大機構を準備
しかしながら、文先生の頭の中には、最初から新しい戦略、しかも奇抜な戦略があったのである。 第一に、時が来るということである。ソ連の滅亡を予言された文先生は、表面上は強大に見えるソ連帝国の内部に、既に衰亡の徴候が現れ、…

爆弾宣言「次の大会はモスクワで」②
しかし、一体どうやって? この点に関しては、誰も言及する者がいなかった。語ることができないのである。なぜか? 到底不可能だからである。 勝共の総帥(そうすい)、文鮮明先生が、勝共の手兵を率いてモスクワに入城したとしょ…

爆弾宣言「次の大会はモスクワで」①
私はすでに、1976年にアメリカの首都ワシントンDCで行われた30万人大会について紹介した。この大会はアメリカ建国200周年記念行事の一環として開催されたものである。「ゴッド・ブレス・アメリカ (God Bless A…

文鮮明師とゴルバチョフ大統領の出会い
<前の記事 1990年4月11日! 不可能なことが創出された日である。到底不可能と思われていた二人の巨人の出会いが実現したのである。信仰の世界では、このようなことを指して「奇跡」と呼ぶ。 一人の巨人は、1960年代以…

ソ連帝国滅亡の予言②
博士自身の言葉を聞いてみよう。 「1985年、ジュネーブで文鮮明師が提唱する世界平和教授アカデミー(PWPA)の『ソ連帝国の崩壊』をテーマにする国際会議が開かれ、私が共同議長を務めました。 当時、ソ連はまだその勢力…

ソ連帝国滅亡の予言①
1985年8月、文鮮明先生が創設された「世界平和教授アカデミー(PWPA)」の第2回国際会議がスイスのジュネーブで開催された。会議の目的は「ソ連共産帝国の崩壊」を予言・宣布することであった。それも5年以内に崩壊するとい…

レーガン大統領、文鮮明師に感謝のメッセージ
1989年1月20日、ジョージ・ブッシュ政権が出帆した。このブッシュ大統領の就任式を見て、8年の間、暴風が吹きすさぶ中で、あらゆる難関を踏み越えて一歩一歩レーガン・ドクトリンを遂行してきたレーガン大統領は、感慨無量だっ…


