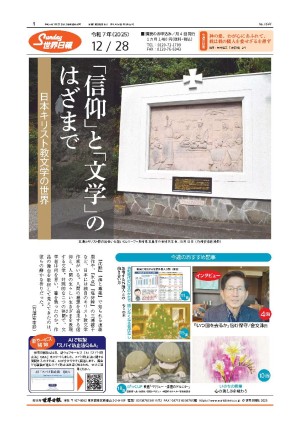沖縄を「日本トレンド」集約地に
一般財団法人沖縄公共政策研究所理事長 安里繁信氏に聞く
沖縄では今、米軍普天間飛行場の辺野古移設をめぐり国と県が対立、過激な移設反対派の活発な運動も相まって、辺野古周辺は緊張状態が続いている。一方、国会では来年度予算の目玉である「地方創生」予算が審議され、県も来年度の「創生」に動きだした。こうした中、将来の沖縄を担う次世代はどのような考えを持ち、今、何に取り組んでいるのか。元日本青年会議所会頭を務め、現在企業10社を取りまとめるシンバホールディングス会長で、一般財団法人沖縄公共政策研究所理事長の安里繁信氏に聞いた。(那覇支局・竹林春夫)
沖縄の保護政策なくなる危機感を
離島振興は国家プロジェクト
――沖縄の経済の現状をどうみるか。すぐに取り組むべき課題は何か。
早稲田大学の某教授によると、韓国の済州特別自治道では、離島の特殊性に配慮した高度な自治が認められているようだ。選任された「大使」が世界中の都市を訪問し、地域間交流に力を入れるなど、特別自治道として自らの生き残りを懸けたビジネス交流を展開している。観光を中心に、医療や教育、IT産業などの幅広い分野への経済の裾野の広がりを目指しており、沖縄が参考にできる先駆的モデルとも言えよう。地方・県・国の単位を超えた地域間交流による主体性ある地方づくりの必要性を痛感している。ロジスティックスの観点から、地の利を生かして勝負すべきと考えている。
しかし、何を売るかが重要だ。沖縄県は、これまでインフラばかりを求め、市場ニーズに合わない物ばかりを生産し、売り込もうとしてきた。香港のある大手旅行会社社長が、「海外の富裕層は沖縄で買いたいものがないから1円も使わずに帰っていく」と語っていた。彼らが求めるのは、夕張メロン、タラバガニ、あまおう(イチゴ)、松阪牛などで、7位のマンゴーは沖縄県産ではなく宮崎県産だった。
観光業で見ると、外国人は単に沖縄を目的として訪日するのではない。日本人が好み愛するリゾート地が知りたいという欲求が強く、安心・安全、かつ東京・大阪・京都などとは異なる未体験の日本を求めている。沖縄で日本を売る。日本のトレンドを売る、という情報発信がとても大事だ。
沖縄が誇る産業の一つに、電照菊に代表される花卉(かき)栽培がある。福岡の花卉市場でも高く評価されており、例えばアジアの花卉マーケットを沖縄に誘致し流通ハブとして位置付けてみてはどうだろう。加えて、沖縄をジャパンカルチャーをも含めたトレンドの一大集約地として位置付け、県外の都市や産地に出向くことなく、沖縄が日本全国からのありとあらゆる産品・ブランドを入手できる流通拠点となれば、経済の飛躍的発展につながる。これを国策として行うことにより、日本経済をもリードするひとつの可能性が広がると思う。沖縄が日本経済に貢献できなければ、これだけの国費を投入する意味はない。これは、私が日本全国津々浦々を訪れ、自分なりに見いだした持論だ。
――平成27年度の沖縄振興策予算が約3340億円。県が政府の振興策の狙いに沿った使い方ができるかどうかが問われている。使う側の責任についてどう考えるか。
県内地方自治体に配分される一括交付金は、補助金等適正化法に照らし合わせれば、厳密には法律にそぐわないとの見方もある。補助金の性質上、通常であれば必要な事業に係る予算を積算し、額が決定するもの。使途が決まっていないにもかかわらず、金額ありきで市町村に頭割りで分配することは本来あってはならないという指摘だ。沖縄は高率補助を受けているという認識を県民は持つべきだ。
県や地自体による負担分(裏負担)が少なくて当たり前という形で、これまで4次にわたる沖縄振興予算が投下され、現在は第5次に突入している。県は振興予算執行の説明責任を果たさなければならないし、逆に政府は使途を検証すべきだ。
――沖縄県は歴史的に所得格差が大きい。県民所得は全国最下位レベルだが、人口に占める所得1000万円以上の割合は全国10位。この問題をどう認識するか。
沖縄の企業はほとんどが中小零細企業である半面、軍用地料を収入とする資産家が多く存在するのが実情だ。また幾つかの産業分野で税制の優遇を受けている業態も存在する。これら優遇措置は、復帰以降ナショナル・ブランドとの競合にさらされる県内業界に対する保護政策であり、前提が時限立法として、係る産業分野が成長・発展するまでと猶予期間が定められている。従って、その恩恵に浴する産業分野においては、本来税制優遇の結果その体質がどう変化したか、競争力は付いたか、個々の企業体質は向上したかなど、きちんと示される必要性がある。
仲井真弘多(ひろかず)前知事県政の1期目に、「沖縄21世紀ビジョン(沖縄振興計画)」を描くに当たり、県内外の有識者による懇話会が招集され、過去40年の振興策の検証を行った。現状、税制の優遇措置を含め、沖縄の振興策がなくなることを前提とした経済ビジョンは描けなかったのだろう。あらゆる分野で、今まで保護の網が掛けられてきた。しかし、いつかは沖縄に対する保護政策がなくなり、自由競争の時代が来るという危機感を持ち合わせておかないと、私たちのリアルな未来像は描けないし、真の経済自立も見通せないだろう。新たな産業も興らない。
――昨年の知事選では基地問題が争点となった。基地問題、安全保障についての考え方は。
安全保障は50年、100年の長いスパンで考えるべきだ。現在、東アジア地域が緊張状態にあり、沖縄は地政学的にリスクと背中合わせの位置にあると言われている。県民であれば、沖縄の米軍基地の整理縮小を誰もが願っている。しかし、米軍普天間基地の移設問題は日米合意である。政治は現実の問題をどう理想に近づけ、解決に導いていくのかを考えなければならない。
――今後の沖縄の地方創生にとって重要なことは。
沖縄公共政策研究所設立のきっかけは離島問題。離島に人が住み続けることは安全保障上、最も重要なことだ。国境地域は古今東西どこも同じで、常に苦々しい思いを強いられている。生活することがハイリスク。このリスクをカバーする「新たな公共」のコンセプトづくりと、政策立案の仕組みづくりが肝要だ。離島振興は経済合理性だけでは計れない国家プロジェクトだと認識している。
=メモ=
あさと・しげのぶ 1969年(昭和44年)沖縄県那覇市生まれ、浦添市育ち。1990年父の経営する「安信輸送サービス(株)」に入社。その後事業を拡大し、2004年シンバホールディングス株式会社代表取締役会長。企業経営の傍ら、那覇青年会議所第38代理事長に就任後、09年には沖縄から初の日本青年会議所第58代会頭を務める。11~13年、沖縄観光コンベンションビューロー(OCVB)会長を経て、13年7月31日、一般財団法人沖縄公共政策研究所を立ち上げ理事長に就任、現在に至る。12年早稲田大学大学院公共経営修士修了、13年4月より早稲田大学総合研究機構公共政策研究所招聘(しょうへい)研究員。日本公共政策学会正会員。