少年法適用年齢引下げの是非
一般社団法人教育問題国民会議理事長・弁護士 秋山 昭八
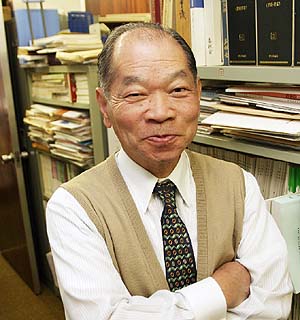 「国法上の統一性」は疑問
「国法上の統一性」は疑問
現行法の「20歳」を踏まえよ
9月10日、自民党の成年年齢に関する特命委員会が取りまとめた提言では、公職選挙法の選挙年齢が18歳以上とされたこと等を踏まえ、「国法上の統一性や分かりやすさ」といった観点から、少年法の適用年齢も20歳未満から18歳未満に引き下げるのが適当としている。
家裁で生育歴などを調べて処分を決めたり、少年院で更生教育を行ったりする現行制度は、有効に機能しているとする反対論は、引き下げによって18歳、19歳の多くがこうした手続きを経ずに不起訴処分や罰金刑だけで終わる可能性があり、「かえって被害者を増やす」と訴えている。
各法律の年齢区分は、その立法目的や保護法益により個別に定められるべきで、少年法の適用年齢は、少年の社会からの逸脱行動にどのように対応するのが立ち直りや再犯防止に有効か、という観点で判断される必要がある。
現行少年法は、全事件を家庭裁判所に送致し、調査官や少年鑑別所による科学的な調査・鑑別の結果を踏まえ、少年に最も相応しい処遇を決する手続きを採用している。このようなきめ細やかな手続きが、生育環境や資質・能力にハンディーを抱える18歳~19歳を含む非行少年の更生に有効に機能してきたのであり、現時点で適用年齢を見直すべき理由はないとする意見や、18~20歳を「青年層」と位置づけ、現在の少年院と同じような教育的処遇を選択できるよう新たな施設を設けるなどの制度設計を提案する説もある。
見直し論は、国法上の成人年齢の統一的な扱いの要請や、マスコミ報道される少年が起こす凄惨な事件などを背景にしているとされる。しかし、この動きに対しては、立法事実の不存在、諸外国の趨勢、脳科学上の知見等の観点から根強い反対論がある。
今次の動きは、「少年事件が非常に凶悪化しており、犯罪を予防する観点から、少年法が今の在り方でいいのか課題になる」旨の与党政務調査会長の発言をも背景とする。しかし、これは明らかな事実誤認である。2000年と2013年の犯罪統計上の数値を比べれば、一般刑法犯の検挙人員のうち年長少年は2万3576人から1万1234人へ、人口10万人あたりの一般刑法犯検挙人員のうち、年長少年は、775・2人から454・7人へと激減している。いわゆる「凶悪犯」も同様である。
「国法上の統一性」という形式的な理由から少年法適用年齢を引き下げることには疑問がある。
年長少年を少年法の適用対象外とすることは、この年齢層について、人間行動科学の専門的知見に基づく教育的な働きかけと非行の背後にある問題に対処する個別処遇から、犯罪の軽重に着目して起訴猶予と略式命令・罰金を多用した画一的対応に転換することを意味する。しかし、こうした転換は再犯予防に優れておらず、刑事政策上の合理性は見いだしがたい。
2013年の各種統計に基づけば、年長少年は、家庭裁判所が受理する一般保護事件の28・7%、少年鑑別所への新収容者の32・4%、保護処分全体の30・6%(保護観察の29・3%、少年院送致の37・8%)を占める。
少年法の適用対象から外せば、1万1744人もの年長少年が刑事司法制度へ放出されることになる。このことは、処遇の質の問題にも直結する。少年司法では個別処遇原則が妥当する。
調査機関に微罪処分や起訴猶予の権限が認められず、犯罪や虞犯となる事由がある場合には全ての事件を家庭裁判所に送致しなければならないものとされていたり、家庭裁判所の判断なしに事件を刑事手続きにのせることができない仕組みが採られていたりするのは、少年鑑別所の鑑別や家庭裁判所調査官の社会調査といった人間行動科学の専門的知見に基づき、この個別な働きかけと処遇を行うためである。
年長少年が少年法の適用対象から外されれば、この年齢層の者の事件は大半が起訴猶予となることが予想される。事件が起訴された場合でも多くは簡便な裁判により財産刑で終局することになることも予想される。
現行法は、少年法適用年齢の上限を旧法の18歳から引き上げ20歳とした。それは当時の犯罪傾向を見た場合に「20歳ぐらいまでの者に特に増加と悪質化が顕著であった」からである。
「この程度の年齢の者は、未だ心身の発育が十分でなく、環境その他外部的絛件の影響を受けやすい」ことから、「刑罰を科するよりは保護処分によってその教化を図る方が適切である」と考えられたわけである。
(あきやま・しょうはち)





