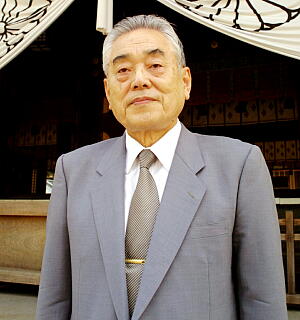中国の防空識別圏に対処を
公海上空の飛行は自由
衝突回避に防衛交流が必要
昨年10月30日、共同通信によれば中国国防省報道官は記者会見で、「自衛隊は緊急発進をやめよ」と声明を発した。ここで次のような批判をした。「日本が公表した緊急発進(平成25年度)は810機であったが、そのうち、中国機に対するものは415機であった。日本戦闘機の中国軍機に対する追跡、監視、妨害は増加している。これが中日間の航空安全問題に関わる問題の根本原因だ。日本は、誤った手法を中止すべきだ」。
自衛隊機は、国際法に基づき領空侵犯阻止のため任務として緊急発進しているのであり、他の目的のため実施しているのではない。中国空軍の国際法規・慣習についての無知による暴言というべき声明だった。
国際条約として、海洋に関しては多種あるが、空に関するものはパリ条約(1919年)を経て、国際民間航空条約=シカゴ条約(1944年)、及び宇宙関連条約などわずかである。海洋法に関する国連条約の中に公海に関する規定がある。同条約によれば、公海とはいずれの国の領海または内水にも含まれない海洋の全ての部分と定義し(86条)、「公海の自由」を強調している(87条)。その中で公海上空の飛行の自由を認めている。一方、国際民間航空条約は、第1条で「主権」として、締約国に領空において完全かつ排他的な主権を有することを承認し、第2条において国の領域を示すことで、公海上空での無害航空の自由を認めている。
「公空」という用語はない。しかし、領土、領海上空を領空と呼称することは、国民にも定着している、日本は海洋国でもあり、拙稿では領空以外の空域を公空として記述しているが、公海上空と解釈されたい。公空における飛行は自由である。
防空識別圏は、防空上の必要に基づき、進入する航空機等の国籍等の識別、位置の確認および必要に応じて飛行に関する指示を行う空域である。同空域に入る航空機等で航空管制機関等に通報なく進入する航空機等で、識別不能のものは、国籍不明機として措置される。わが国では、航空自衛隊で戦闘機を緊急発進させ、識別、確認および所要の措置を行う。
防空識別圏の設定自体は自由であり、接壌国間でも設定できる。しかし、そのためには高性能レーダーや通信設備によるほかはない。戦闘機を緊急発進して、他国の領域に侵入し識別、監視はできない。平成25年11月に中国は東シナ海に尖閣諸島を含み、従来の防空識別圏と異なる概念の防空識別圏を一方的に設定した。
自衛隊が緊急発進するのは、他国の航空機が無法に、日本領空に侵入することを防止するためである、防空識別圏内に進入した航空機に対して、規定に基づき、安全を考慮し、進入機と一定の距離を保持しつつ慎重に飛行し、その行為を妨害し、威嚇的行為をすることはない。
平成13年、中国戦闘機は、東シナ海公空で、威嚇のためか,哨戒飛行中の、米EP3偵察機に異常な接近をし、衝突、墜落し、操縦士は死亡した事件があった。軍は彼を光栄ある戦士として,賞賛した。昨年5月、6月には日本の防空識別圏内で中国戦闘機が自衛隊機に繰り返し異常接近し、また、8月には南シナ海公空で米軍機に対し10㍍と衝突寸前の距離まで威嚇的に接近した。米国の強い抗議に対しても「米偵察機を追い払うことは、中国の核心的利益だ」(環球時報)と高言している。
防空識別圏の設定は公空であれば制限されないが、識別のため緊急発進して他国の領空への飛行は、国際航空条約による主権の侵害であり許されない。中国は平成2年、領域法により、尖閣諸島を自国領として一方的に定め、核心的利益と称し、その確保のためには、軍事力の運用すらも躊躇(ちゅうちょ)せぬような強い決意である。中国の防空識別圏発表を受け、ウォール・ストリート・ジャーナル紙は、「この設定は、日本との緊張を高める無謀な瀬戸際政策であり、あからさまな侵略行為に近づいた。中国は威嚇行為の危険性を自覚せよ」と警告している。日中間の諍(いさか)が、偶発的に軍事的衝突にエスカレートするとの懸念は、海外では予想以上に強い。
中国は、接近阻止・領域拒否戦略の一環としてか、領域に接しての偵察を拒否するため、「国家の主権及び国防安全のため、自国の空中管理の条件下に、公海から経済水域を除外する」と規定し、防空識別圏を設定したようで、戦闘機の行動はそれを実行したと推測できる。
昨年12月10日に日本経済新聞は「日本とロシアは航空自衛隊とロシア空軍による防衛交流に乗り出す。空自幹部が週明けにハバロフスクでロシア空軍幹部と会談し、輸送機部隊の相互訪問開始などについて話し合う。3月のウクライナ危機以降、日本領空周辺でロシア機の動きが活発になっており、空域での意思疎通を深め、衝突など不測の事態を防ぐ狙いだ」と報じた。日中両国間でも公空および防空識別圏を明確にし、そこにおける飛行の自由を保持できるように立法を切望する。尖閣上空侵犯問題の処理は、国際世論に配慮し、情報戦を重視し、特に武器使用は慎重にすべきである。
(たけだ・ごろう)