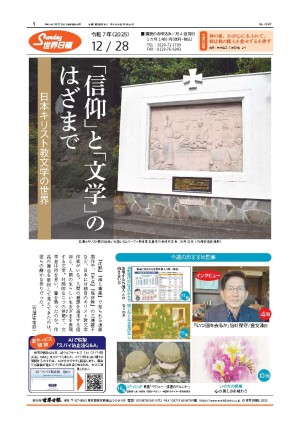「一つの中国」は中国の主張
トランプ政権と米中台関係
評論家 黄文雄氏
「中華民族の偉大な復興」を掲げ、強権台頭の陣頭指揮を執る中国の習近平国家主席。一方、先月20日就任した米国のトランプ大統領は、貿易問題や海洋進出問題、さらに台湾問題で、中国に対し厳しい姿勢を示している。評論家の黄文雄氏に、「一つの中国」問題やトランプ時代の日本の役割を聞いた。(聞き手=池永達夫)
トランプ発言、台湾は取引材料化を懸念
トランプ氏は米大統領就任前、「『一つの中国』に縛られない」と発言した。これは米の対中外交の転換を示唆したものなのか?

こう・ぶんゆう 1938年12月5日、台湾生まれ。早稲田大学卒。文明史・経済史研究者にして哲学者。専攻は西洋経済史。拓殖大学日本文化研究所客員教授。主権回復を目指す会顧問、世界戦略総合研究所評議員。和・漢両棲類ノンフィクション作家。
中国は激怒したが、トランプ氏とすれば当然のことを言ったに過ぎない。
そもそも1972年2月にニクソンが訪中し、毛沢東と交わした米中共同宣言(上海コミュニケ)では「『中国は一つであり、台湾は中国の一部である』との中国の主張を米国は認識する」とある。
「一つの中国」はあくまで中国の主張だ。日本政府の立場も「中国の主張に対し理解し尊重する」というものだ。さらに米国には台湾関係法があって、台湾の安全を守る義務がある。
ただ、多くのマスメディアは「一つの中国」を中国政府の言う通りに、そのまま鵜呑(うの)みにしている。その意味では基本的な歴史認識が欠落していて、テレビも新聞も底が浅い。
それでも中国には激震が走った?
中国外務省スポークスマンは、「トランプ新政権は台湾問題の高度な敏感性を十分に認識し、『一つの中国』政策を堅持し、慎重かつ適切に問題に対処すべきだ」と改めてクギを刺した。
一方で台湾の蔡英文総統は静観している。敢(あ)えて火中の栗を拾い中台関係悪化を招くような事態を避けるとともに、トランプ政権が台湾カードをバーゲニングパワーにして、中国を揺さぶっているだけではないかとの懸念があるためだ。
京大教授だった勝田吉太郎氏に「共産主義の本質は何か」と尋ねた時、「嘘(うそ)と暴力」だと答えた。
共産党というのはやくざ組織に近い。嘘で言いくるめ、それが効かないと力で押してくる。
「92年コンセンサス」も同じか?
中台の交流窓口機関が1992年に、中国大陸と台湾は不可分であるとする「一つの中国」原則を口頭で認め合ったという「92年コンセンサス」は、台湾側窓口機関海峡交流基金会の辜振甫理事長や李登輝総統(いずれも当時)すら「合意などない」と否定しているにもかかわらず、中国は一方的に押し付けてきている。習近平国家主席は「92年コンセンサスを認めなければ現状維持もない」と脅しているが、中国の常套(じょうとう)手段である「無から有を創り出す」餌食になってはならない。
虚言を語る中国人のルーツは、漢語文化だというのが黄氏の持論だが?
漢語は美辞で虚飾的だから、美化し賛美するのに便利な文字だ。その意味では、嘘がそもそも漢語の中に入っている。
また、漢語は最も原始的な単語音から成るもので、口語の語彙(ごい)が漢語以外の言語に比べ、不足している。そのため大きな声と大げさな手ぶり身ぶりで言語の不足を補わなければならない。
漢語は構造的論理性が欠如しているので、中国人の主張はたいてい矛盾だらけだ。相手に「道理」を説くよりも問答無用の「恫喝(どうかつ)」しかないのは、主にこの漢語の言語構造からくるもので、「話せば分かる」人間ではない。
一方で日本は、1000年以上も前にカナ文字という表音文字を創出しただけでなく、漢字カナ文字交じりの文章体系を創出した。表意・表語文字である漢字という視覚のメディアと、カナという表音の聴覚的メディアを習合した、まったく新たな視聴複合的メディア体系を確立したことで、複雑な思考や感情を極めて的確に表現することができるようになった。
日本に列強の調整期待
中国、いずれ露・印と衝突
現実的に台湾が守られているのは台湾関係法があるからだ。米がバックに控えている。
しかし、米がいざという時、守ってくれるかどうかという問題がある。
三つの障壁があって、大統領と議会、それに国民の意識がそれだ。この3者の意見が相違すると、スムースにはいかない。いくらトランプ大統領が動いても、国民の世論をバックに議会が承認しないとなかなか動けない。
トランプ大統領の米国第一主義がモンロー主義に陥る懸念は?
トランプ大統領は、モンロー主義というよりレーガン時代に戻ろうとしているのではないか。大型減税や金融規制の緩和などを掲げて、レーガノミクスに近い。「偉大な米国の復活」というスローガンは、冷戦を終結させたレーガン時代を指しているのではないか。
日本はその意味で、大きなチャンスの時だと思う。
世界は反グローバリズムの列強時代に戻りつつある。そうした時代には調整役が不可欠だ。日本はその調整役になるいい位置にいる。
中国崩壊論が出ているが?
崩壊までには至らないだろう。なぜかというと、大躍進の失敗で経済が100%駄目になり、餓死者は2500万人から8000万人まで出した。それでも中国は国として崩壊しなかった。要するに中国というのは原始社会に戻っても、崩壊しない。
崩壊の定義は、経済崩壊か、国家崩壊か、社会崩壊か、文明崩壊か、概念規定が大事だ。だから崩壊といっても、みんなそれぞれにばらばらに考えている。
大体が経済中心の考えだが、中国の歴史を見ると、文化大革命で経済が崩壊し、すべて崩壊したが、軍だけ残った。その軍がまた新しい中国を作り直した。
何が一番影響があるかというと、サーズや鳥インフルエンザといった感染症のパンデミックだ。それさえ無ければ、中国は原始社会に戻っても生き残る。あの国というのは権力の源泉は軍にある。
中国崩壊の代わりに、カタストロフィーやメルトダウンというのがふさわしいのではないか。
習国家主席はその軍を完全に掌握しているのか?
まだだろう。7大軍区から5軍区に統合したが、それが機能するようになるまでに最低5年はかかる。その間、戦争はできない。
中国共産党の最大の目的は、政権の維持だ。内部矛盾を隠蔽(いんぺい)するため、国民の目を外に転じるための戦争リスクは常に存在するのでは?
中国も台湾も、ともに通商国家だ。戦争となると海上封鎖も起きる、とたんに経済麻痺(まひ)だ。それだと中国は台湾と共倒れになる。
20世紀から現在まで、中国の三つの敵というのは、日本軍国主義と米帝国主義と台湾分裂主義だった。しかし、これからは海の日本と陸のインドということになるだろう。
中国は伝統的に「遠交近攻」の国だ。いつかは隣国のロシア、インドとぶつからざるを得ない。それは歴史が物語っている。中印露の「三国志演義」が繰り返される中で、日米露が提携すれば、中国包囲が可能だ。ユーラシア大陸の陸と海から全体的に見ないと、中国の覇権主義がどうなっていくのか読めない。