自分史ブーム 書いて日本を元気に
一般社団法人自分史活用推進協議会代表理事 前田義寛氏に聞く
自分史が静かなブームになっている。従来からの自伝、自叙伝が成功者の立志伝という意味合いが強いのに対して、一般人が自分の人生を回想して書き綴(つづ)り、自費出版するものと言えよう。一般社団法人自分史活用推進協議会の代表理事で、自分史講座を開いている前田義寛(よしひろ)さんにブームの背景を聞いた。
(聞き手=フリージャーナリスト・多田則明)
残したい「生きた証し」/負の遺産も生きる力に
新たな勇気得て人生再出発/仲間ができる楽しさや共感も
――2010年に自分史活用推進協議会をつくられた経緯は?
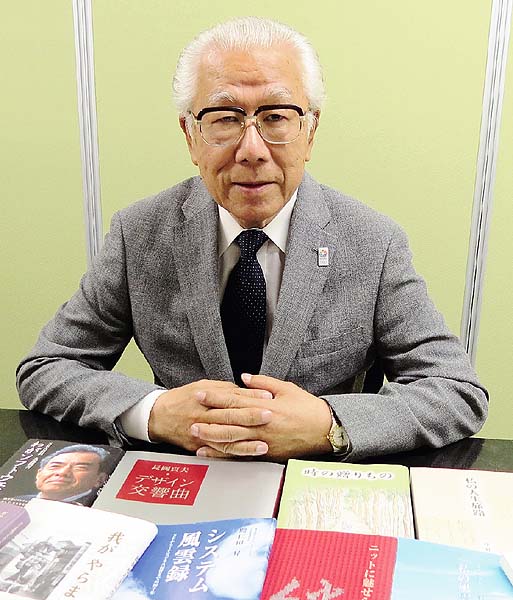 私は編集者として企業の広報関係の仕事をしてきた関係から、創業者や経営者に接する機会が多く、自分史の作成を依頼されることもありました。そうした中で一般の人たちが個人の歴史を残すことに関心が深まり、同じ考えの人たちと相談して自分史活用推進協議会の設立に参加しました。
私は編集者として企業の広報関係の仕事をしてきた関係から、創業者や経営者に接する機会が多く、自分史の作成を依頼されることもありました。そうした中で一般の人たちが個人の歴史を残すことに関心が深まり、同じ考えの人たちと相談して自分史活用推進協議会の設立に参加しました。
協議会では3年ほど前から自分史のセオリーをまとめ、自分史活用アドバイザー認定制度を設けました。2013年から「自分史フェスティバル」を開いて、自分史のすべてをプレゼンテーションしています。昨年のフェスティバルでは、立教セカンドステージ大学で講座を開き、『自分史の書き方』を著した立花隆さんが記念講演をしました。
メディアでも自分史が取り上げられ、特に今年は戦後70年ということで、高齢世代の中で戦争体験などを語り継ぎ、記録に残したいという人が増えています。
――自分史を書こうとする一般の人にどんなアドバイスをしますか。
かつては功成り名遂げた人が、人生を回想する伝記的な要素が強かったのですが、今は庶民の間で自分史が広まっています。庶民の歴史に関心が持たれるようになったのは、色川大吉さんが『ある昭和史―自分史の試み』を1975年に書いてからとされています。色川さんは近現代史研究の中で常民の記録を調べ、それを「自分史」として世に問うたのです。
一般市民の自分史が注目されるようになったのには、出版不況の中で需要を掘り起こしたい業界の動きもあります。自費出版がビジネスになったのが1980年代です。もう一つは、80年代に文部省が生涯学習を掲げ、カルチャーセンターなどの活動が盛んになりました。そうしたことで社会全体の知的活動が活発になってきたのです。
自分史は自己責任で行う執筆・本作りで、自分が書きたいように、伸び伸びと書けばいいのが特徴です。しかし、自費出版とはいえ第三者に読んでもらうのですから、読みやすく、間違いのないようにし、読み手に不快感を与えたり、誰かを傷つけたりすることは避けないといけません。
――高学歴化、高齢化で、定年後の長い時間の過ごし方が課題になっています。
高齢になると、多くの人が自分の生きた証しを残したいと思うようになります。そうしたニーズとシーズが合わさったのが今の自分史の流行かと思います。普通の人が自分史を書き、立派な本だけではなく、手作りの冊子などにしています。
――人生のどんな記録を残したいのですか。
人生には明と暗の両面がありますが、その両面を残したいという人が増えています。人生の負の部分が心のしこりになっている方は、自分史に書くことによって、それが負ではなくなる、振り返り整理してみて出来事の必然性が理解できたり、誤解が解けたりすることもあるようです。書くことで勇気が出たり、吹っ切れたりすることが高齢者にはよくあります。自分史には心の浄化作用もあることを痛感します。
協議会のキーワードは「自分史を書いて日本を元気に」です。自分史を書いて過去が整理できると、高齢者が残されて人生を新たな勇気で生きていくことができます。自分史を出したのがきっかけで古い付き合いが復活したり、新しい楽しみにつながったりしています。そんなことが広がれば日本はもっと元気になります。特に3・11以後は国民的に生きる意味を問い直す風潮があり、自分史にもそれなりの役割があるように思います。
私は終戦時に10歳で、疎開していた福井で空襲に遭いました。戦争体験者が少なくなり、それぞれの戦争体験を伝えたい高齢者がいる一方で、戦争を知りたいという若い世代が多くなっています。私は市民ビデオのコンクールにもかかわっていますが、高校生や大学生が日中戦争や沖縄戦について現地を取材し、生き残りの元兵士に話を聞いた作品がありました。語り伝えると同時に、戦争を知らない世代が戦争について学び始めているのです。自分史でも、その両者の接点を大事にしたいと思っています。
――自分史を書く意味は?
誰しも負の遺産を持っていますが、自分史を書くことで解消され、生きる力になるケースもあります。自分史活用アドバイザーとして、ここまで書いていいのかと思うこともあります。遺産相続の争いを書くという人に、そこまで書かなくてもいいのではとアドバイスしたのですが、子供たちに伝えるためにどうしても書くという人もいました。
自分史は自己完結の世界ですが、講座などに来ると仲間ができる楽しさがあります。同世代としての共感や、それぞれの生き方への興味などで、いわば自分史コミュニケーションが育っています。個人の営みのはずの自分史が、つながりができることで知的な広がりが生まれているのです。
自分史を書いた多くの人が最後に感謝の気持ちになっています。父母や先祖への感謝で、「父と母への感謝をこめて」と書く人もいます。当然ですが、自分一人で生きた人生ではなく、お世話になった人たちを思い出すわけです。
――日本人には先祖は神になり子孫を見守っているという他界観があります。
普段は意識していなくても、自分史を書くことで先祖の恩に目覚める人がいます。自分の原点を探ると、先祖に行き着きますから。私たちは8月7日を「自分史の日」に定めました。8と7で話に花を咲かせるという語呂合わせですが、自分史の始まりは話すことで、先祖をお迎えするお盆の前なのも意味があります。
――ITの発展も自分史作りを後押ししています。
パソコンやインターネットなどITツールを使って効果的に自己発信ができるようになりました。大きな変化は、内にではなく外に向けて発信する自分史になったことです。ネット上に公表したり、本をネットで販売したりしています。
ライフログという言葉がありますが、日常生活を長期間にわたってデジタルデータとして記録する若い人が増えてきました。ブログもその一つで、自分史の多様化が始まっています。
――オンデマンドで本を1冊から製作できるようになっています。
ビジネスとしての自分史は5万円でできるものから300万円かかるものまで多様で、人それぞれの価値観に応じて選べるようになっています。そうした機器やシステムの進化も自分史ブームを後押ししています。





